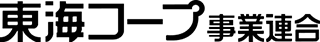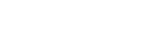おいしくって安全なお話2025年39号(安心して食べるために~情報に振り回されないコツ~)
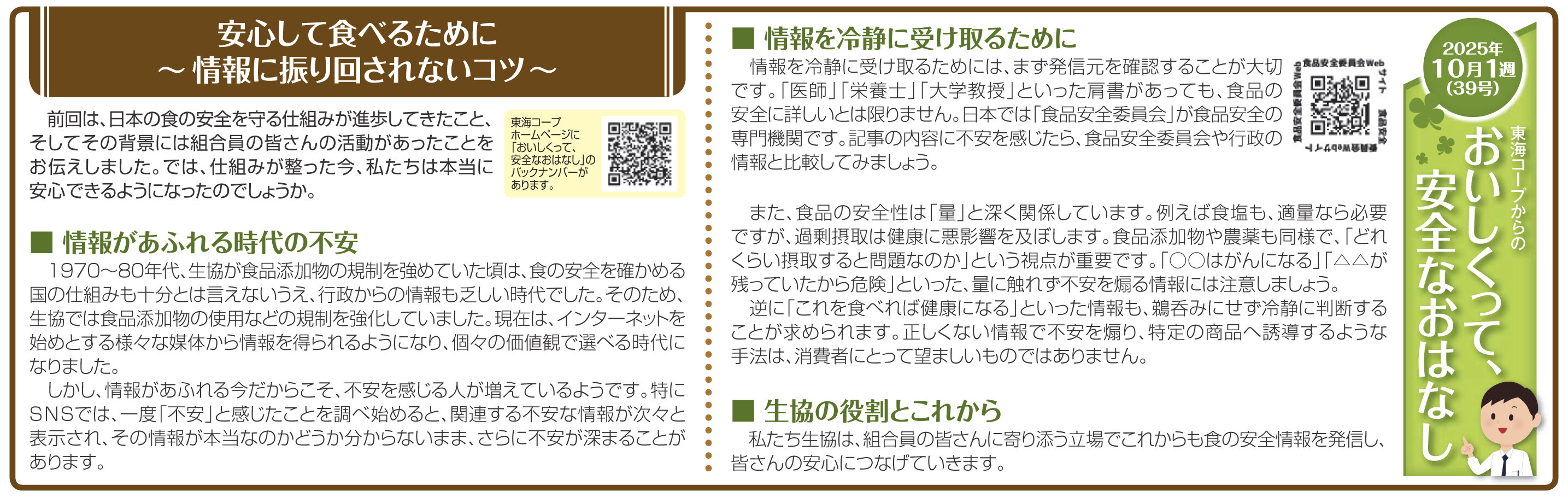 39号‗安心して食べるために~情報に振り回されないコツ~.pdf
39号‗安心して食べるために~情報に振り回されないコツ~.pdf
前回は、日本の食の安全を守る仕組みが進歩してきたこと、そしてその背景には組合員の皆さんの活動があったことをお伝えしました。では、仕組みが整った今、私たちは本当に安心できるようになったのでしょうか。
■ 情報があふれる時代の不安
1970~80年代、生協が食品添加物の規制を強めていた頃は、食の安全を確かめる国の仕組みも十分とは言えないうえ、行政からの情報も乏しい時代でした。そのため、生協では食品添加物の使用などの規制を強化していました。現在は、インターネットを始めとする様々な媒体から情報を得られるようになり、個々の価値観で選べる時代になりました。
しかし、情報があふれる今だからこそ、不安を感じる人が増えているようです。特にSNSでは、一度「不安」と感じたことを調べ始めると、関連する不安な情報が次々と表示され、その情報が本当なのかどうか分からないまま、さらに不安が深まることがあります。
■ 情報を冷静に受け取るために
情報を冷静に受け取るためには、まず発信元を確認することが大切です。「医師」「栄養士」「大学教授」といった肩書があっても、食品の安全に詳しいとは限りません。日本では「食品安全委員会」が食品安全の専門機関です。記事の内容に不安を感じたら、食品安全委員会や行政の情報と比較してみましょう。

また、食品の安全性は「量」と深く関係しています。例えば食塩も、適量なら必要ですが、過剰摂取は健康に悪影響を及ぼします。食品添加物や農薬も同様で、「どれくらい摂取すると問題なのか」という視点が重要です。「○○はがんになる」「△△が残っていたから危険」といった、量に触れず不安を煽る情報には注意しましょう。
逆に「これを食べれば健康になる」といった情報も、鵜呑みにせず冷静に判断することが求められます。正しくない情報で不安を煽り、特定の商品へ誘導するような手法は、消費者にとって望ましいものではありません。
■ 生協の役割とこれから
私たち生協は、組合員の皆さんに寄り添う立場でこれからも食の安全情報を発信し、皆さんの安心につなげていきます。
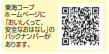
東海コープ