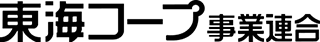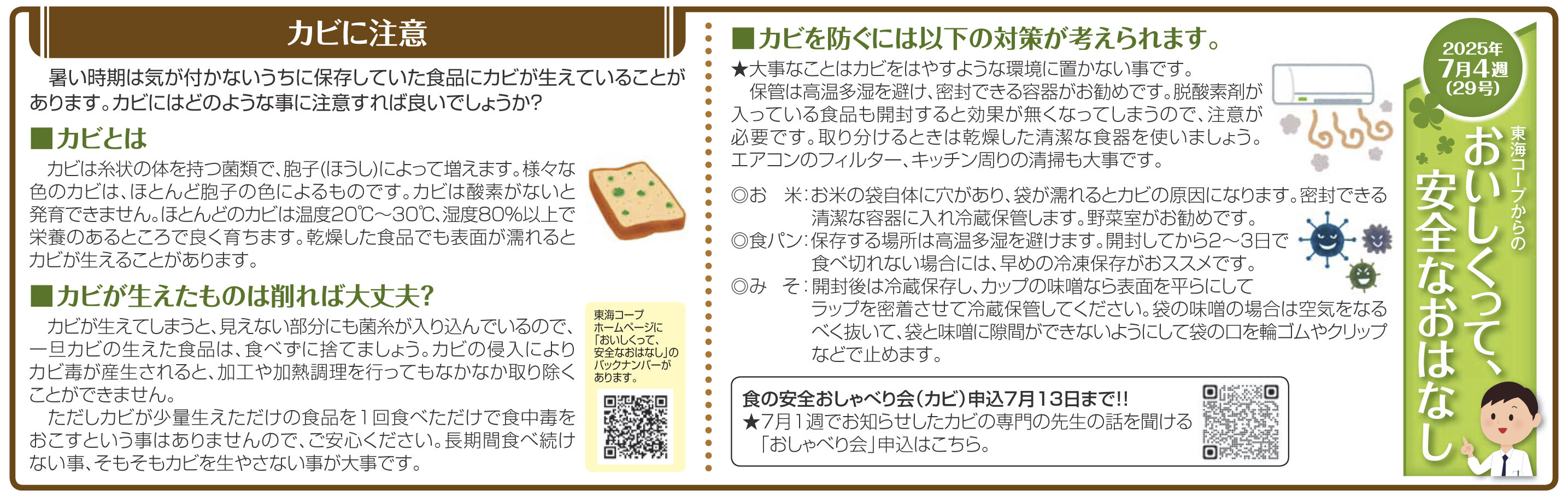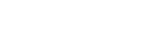おいしくって安全なお話2025年29号(カビに注意)
暑い時期は気が付かないうちに保存していた食品にカビが生えていることがあります。カビにはどのような事に注意すれば良いでしょうか?
■カビとは
カビは糸状の体を持つ菌類で、胞子(ほうし)によって増えます。様々な色のカビは、ほとんど胞子の色によるものです。カビは酸素がないと発育できません。ほとんどのカビは温度20℃~30℃、湿度80%以上で栄養のあるところで良く育ちます。乾燥した食品でも表面が濡れるとカビが生えることがあります。

■カビが生えたものは削れば大丈夫?
カビが生えてしまうと、見えない部分にも菌糸が入り込んでいるので、一旦カビの生えた食品は、食べずに捨てましょう。カビの侵入によりカビ毒が産生されると、加工や加熱調理を行ってもなかなか取り除くことができません。
ただしカビが少量生えただけの食品を1回食べただけで食中毒をおこすという事はありませんので、ご安心ください。長期間食べ続けない事、そもそもカビを生やさない事が大事です。
■カビを防ぐには以下の対策が考えられます。
★大事なことはカビをはやすような環境に置かない事です。
保管は高温多湿を避け、密封できる容器がお勧めです。脱酸素剤が入っている食品も開封すると効果が無くなってしまうので、注意が必要です。取り分けるときは乾燥した清潔な食器を使いましょう。エアコンのフィルター、キッチン周りの清掃も大事です。

◎お 米:お米の袋自体に穴があり、袋が濡れるとカビの原因になります。密封できる清潔な容器に入れ冷蔵保管します。野菜室がお勧めです。
◎食パン:保存する場所は高温多湿を避けます。開封してから2~3日で食べ切れない場合には、早めの冷凍保存がおススメです。
◎み そ:開封後は冷蔵保存し、カップの味噌なら表面を平らにしてラップを密着させて冷蔵保管してください。袋の味噌の場合は空気をなるべく抜いて、袋と味噌に隙間ができないようにして袋の口を輪ゴムやクリップなどで止めます。

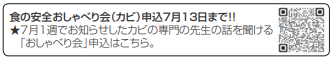

東海コープ