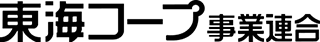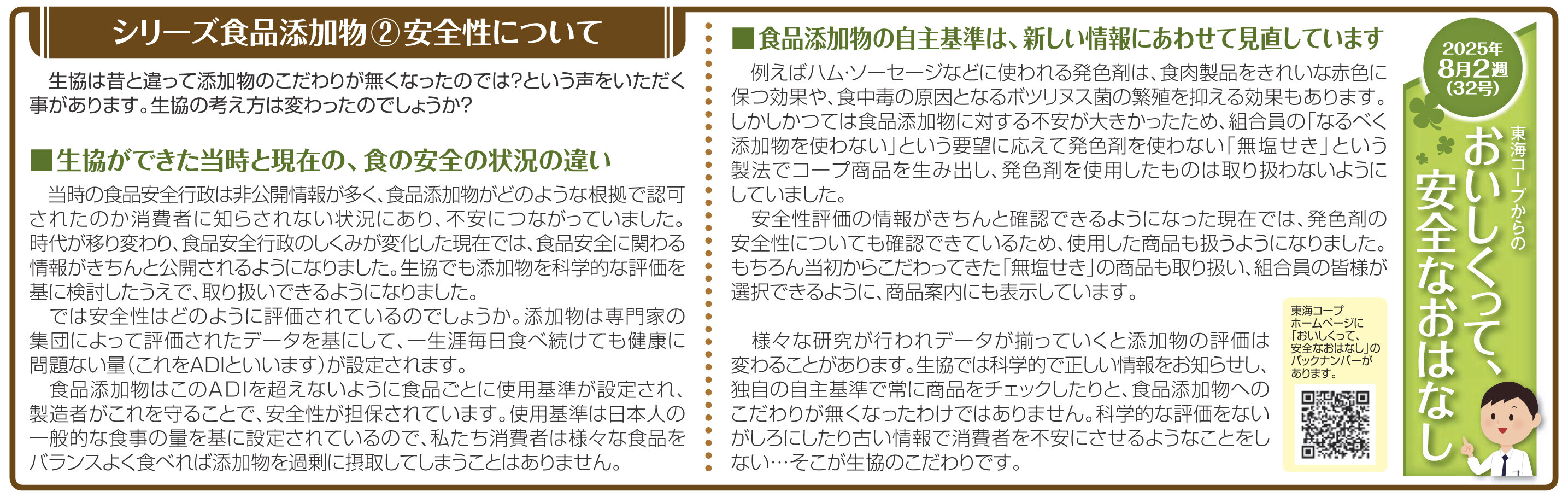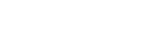おいしくって安全なお話2025年32号(シリーズ食品添加物②安全性について)
生協は昔と違って添加物のこだわりが無くなったのでは?という声をいただく事があります。生協の考え方は変わったのでしょうか?
■生協ができた当時と現在の、食の安全の状況の違い
当時の食品安全行政は非公開情報が多く、食品添加物がどのような根拠で認可されたのか消費者に知らされない状況にあり、不安につながっていました。時代が移り変わり、食品安全行政のしくみが変化した現在では、食品安全に関わる情報がきちんと公開されるようになりました。生協でも添加物を科学的な評価を基に検討したうえで、取り扱いできるようになりました。
では安全性はどのように評価されているのでしょうか。添加物は専門家の集団によって評価されたデータを基にして、一生涯毎日食べ続けても健康に問題ない量(これをADIといいます)が設定されます。
食品添加物はこのADIを超えないように食品ごとに使用基準が設定され、製造者がこれを守ることで、安全性が担保されています。使用基準は日本人の一般的な食事の量を基に設定されているので、私たち消費者は様々な食品をバランスよく食べれば添加物を過剰に摂取してしまうことはありません。
■食品添加物の自主基準は、新しい情報にあわせて見直しています
例えばハム・ソーセージなどに使われる発色剤は、食肉製品をきれいな赤色に保つ効果や、食中毒の原因となるボツリヌス菌の繁殖を抑える効果もあります。しかしかつては食品添加物に対する不安が大きかったため、組合員の「なるべく添加物を使わない」という要望に応えて発色剤を使わない「無塩せき」という製法でコープ商品を生み出し、発色剤を使用したものは取り扱わないようにしていました。
安全性評価の情報がきちんと確認できるようになった現在では、発色剤の安全性についても確認できているため、使用した商品も扱うようになりました。もちろん当初からこだわってきた「無塩せき」の商品も取り扱い、組合員の皆様が選択できるように、商品案内にも表示しています。
様々な研究が行われデータが揃っていくと添加物の評価は変わることがあります。生協では科学的で正しい情報をお知らせし、独自の自主基準で常に商品をチェックしたりと、食品添加物へのこだわりが無くなったわけではありません。科学的な評価をないがしろにしたり古い情報で消費者を不安にさせるようなことをしない…そこが生協のこだわりです。

東海コープ